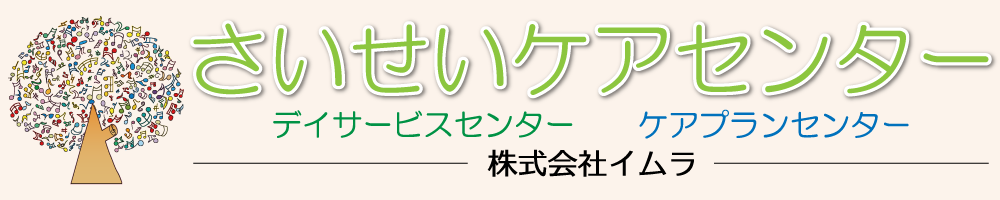虐待の発生・再発防止のための指針
1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
2006(平成 18)年4月1日に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する 支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という。)第1条第1項において、その 目的が規定されている。
高齢者虐待防止法
第1条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持 にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、 高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護 のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高 齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防 止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護 に資することを目的とする。高齢者虐待防止法第 2 条第1項において、「高齢者」とは 65 歳以上の者としている。 また、同条第3項において、高齢者虐待を、①養護者による高齢者虐待、及び②養介護施 設従業者等による高齢者虐待に分けて定義している。
※ 「養護者」…高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの
※ 「養介護施設従業者等」…養介護施設及び養介護事業の従事者
2 本指針の目的
この指針は、さいせいケアプランセンターが運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように支援することを目的とします。
3 基本的考え方
当事業所では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為と言う認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に勤め、高齢者虐待に該当する次の行為いずれも行いません。
◎身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
◎介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
◎心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢 者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
◎性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行 為をさせること。
◎経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に 財産上の利益を得ること。
4 虐待防止に向けた体制(虐待・事故防止委員会の設置)
- 当事業所内での高齢者虐待の発生及びその再発を防止するとともに、発生時における対 応が迅速に行われ、かつ、利用者及び家族等に最善の対応を提供することを目的として、 虐待防止に係る管理体制を事業所全体で取り組むため、虐待・事故防止委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
- 委員会は、当事業所の介護支援専門員で構成する。なお、委員長は管理者とし、副委員長は選任された高齢者虐待防止に関する責任者とする。
- 委員会は、1年に1回以上開催し、虐待防止策等の検討を行う。また、虐待発生時等において、必要に応じ、臨時委員会を開催する。
- 委員会の役割は、次のとおりとする。
- 事業所内における虐待防止対策の立案
- 指針・マニュアル等の整備・更新
- 虐待予防のための具体策の検討
- 虐待予防策実施状況の把握と評価
- 高齢者虐待発生時の措置(対応・報告(通報))
- 研修・教育計画の策定及び実施
- 高齢者虐待防止推進のための担当者は、委員会の委員長とする。
6 虐待の早期発見の対応
- 日々における利用者の生活状況や身体状況等、様々な面でのモニタリングにより、高齢者虐待の兆候を早期に発見するように努めるとともに、兆候が現れた利用者等に関しては、速やかに事業所内において現状や経過等の把握に努める。
- 責任者は、情報を集約するとともに分析し、虐待の有無を検証する。なお、虐待の可能性があると判断した場合は、委員会の委員長(以下、「委員長」という。)に対し報告する。
- 委員長は、臨時委員会の開催の可否を決定するとともに、委員会を開催する場合にあっては、報告された案件の内容を適切に審査し、虐待であると判断した場合は再発防止策を検討するものとする。
7 虐待を発見した場合の通報等
- 職員は、高齢者虐待の早期発見に努め、高齢者虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、又は、当該利用者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村、地域包括支援センター等に通報しなければならない。【通報義務】(高齢者虐待防止法第7条第1項及び第2項)
- (1)の通報をすることは、守秘義務の違反にはならない。(高齢者虐待防止法7条第3項)
8 虐待防止のための職員研修
- 当事業所の介護支援専門員に対し、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、基本的な学習を行い、常に適正な介護支援に努めることとする。また虐待につながる不適切ケアの研修や事例検討によって、介護支援専門員らが意識を高め、実践につなげることとする。
- 高齢者虐待防止法の仕組みと留意すべき点を理解する。
- 研修は、新規採用者に対する研修のほか、定期研修を年1回開催する。
9 成年後見制度の利用支援
精神上の障害により、判断能力が不十分であるため法律行為における意思決定が困難な方々の権利擁護を図るために制定された成年後見制度を、利用者及び家族等が円滑に利用することができるよう、関係機関等と連携するなどして必要な支援に努める。
10 虐待等に係る苦情解決の徹底
高齢者虐待を防止するため、当事業所では、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決するよう最大限努力するものである。
11 利用者等に対する当該指針の閲覧について
本指針を事業所内に掲示すると共に、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにする。
12 その他虐待の防止の推進のために必要な事項
7に定める研修会のほか、各関係期間により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護に関する理解を深め、常に研鑽を図る。